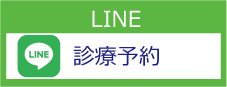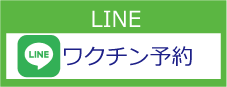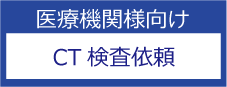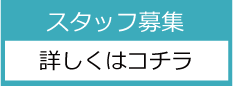対応出来る疾患
・狭心症・心筋梗塞・不整脈・心臓弁膜症・肥大型心筋症・拡張型心筋症・解離性大動脈瘤
・胸部大動脈瘤・腹部大動脈瘤・高血圧症・低血圧症・糖尿病・メタボリック症候群
・脂質異常症(コレステロール・中性脂肪が高い)・ニコチン依存症
・深部静脈血栓症・血栓性静脈炎・下肢静脈瘤・片頭痛・その他内科一般
狭心症
症状
冠動脈が狭くなり、一時的な心筋虚血に陥る状態をいいます。典型的な胸痛(胸の不快感、圧迫感、締め付けられる感じ)はもちろん、喉や顎に放散する痛み、左肩や上腕の嫌な感じやしびれ感が狭心症の症状である可能性もあります。冷汗を伴っていれば重症である可能性もあります。狭窄の原因の多くは動脈硬化ですが、血管が痙攣して狭窄し症状を起こすこともあります。動脈硬化は血管の内側にコレステロールがたまって粥状の塊ができ、血管の内腔を狭くします。血管の老化現象と関係があり、中高年から急増しますが、近年は若い人にも増えています。
心筋梗塞
 冠動脈が閉塞することによって心筋に血流がいかなくなり(虚血)、その部分の心筋が死んでしまう(壊死)状態をいいます。閉塞する原因は粥種(コレステロールがたまって出来る粥状の塊)の破裂に伴う血栓形成によるものが大半を占めてます。
冠動脈が閉塞することによって心筋に血流がいかなくなり(虚血)、その部分の心筋が死んでしまう(壊死)状態をいいます。閉塞する原因は粥種(コレステロールがたまって出来る粥状の塊)の破裂に伴う血栓形成によるものが大半を占めてます。
症状
突然発症し、30分以上続く強い前胸部痛が80%~90%を占めますが、呼吸困難、息切れ、失神発作など非典型的な場合もあります。また5%ほどは無症状で経過し、健康診断などで後になって診断される事があります。特に糖尿病合併者や高齢者ではその傾向が強く、症状が明確でない事があります。不整脈
症状
ドキッとしたり、ドキドキしたり、色々な症状が出ます。しかし、自覚症状は患者さんによって異なります。動悸を訴える人が多いのですが、何も感じない人もいます。なぜ人によって症状が違うのか、その理由については、今のところ分かっていません。
生活習慣病
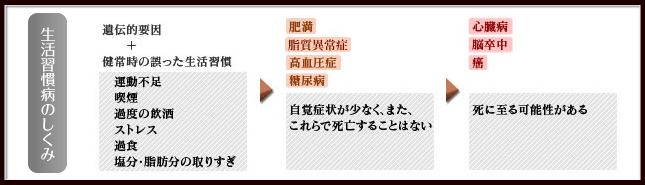
★高血圧★
日本人の大部分が本態性高血圧と呼ばれる高血圧で、その他に腎動脈の狭窄、甲状腺や副腎という臓器から出るホルモンが原因で起こる二次性高血圧があります。生活習慣病に関係するのは、本態性高血圧です。本態性高血圧は、その体質が遺伝しやすい事が知られています。
◆本態性高血圧はどうしておこるの? -腎臓が大きな役割ー
 人は魚から進化しました。塩(NaCl)の豊かな海水から、塩(NaCl)にいつありつけるか分からない、陸上での生活に適応するように進化する過程で、塩(NaCl)を体の中に貯めておく機能が発達したのです。
人は魚から進化しました。塩(NaCl)の豊かな海水から、塩(NaCl)にいつありつけるか分からない、陸上での生活に適応するように進化する過程で、塩(NaCl)を体の中に貯めておく機能が発達したのです。その働きを担っているのが腎臓です。ところが、文明社会が発達し、塩(NaCl)が調味料として贅沢に使えるようになると、余分に摂取した塩(NaCl)を腎臓から排泄しなければならなくなりました。
正常の血圧では、余分な塩(NaCl)を排泄できない腎臓の機能であるため、血圧を上昇させることにより、余分な塩分(NaCl)を排泄させる必要が出てきました。これが高血圧なのです。高血圧は、いわば進化のプロセスに逆行して、人類が塩(NaCl)の過剰摂取をした結果といえるのです。
◆高血圧を放置すると、どうなるの?
また、内皮細胞がはがれると、そこに血のかたまりである”プラーク”ができている場合には、それを破裂させます。破裂した”プラーク”にも血栓ができていますので、心臓の冠動脈に血栓ができれば心筋梗塞が起こり、脳の動脈に血栓ができれば脳梗塞が起きます。また高血圧は動脈を破裂させます。
◆高血圧を放置すると、どうなるの? ~心臓の筋肉への影響~
高血圧は全身の動脈に影響して、動脈硬化を進行させ動脈を閉塞させたり、動脈を破裂させたりします。もう一つの重要な影響は、心筋(心臓の筋肉) に対するものです。
血圧が高くなると、心臓は高い血圧に打ち勝とうとするため収縮力を高めます。収縮力を高めるために、心筋を肥大させることにより適応するわけです。スポーツ選手がトレーニングをして全身の筋肉をつけるのと違って、心臓自身が肥大することは、心臓そのものの負担となります。高血圧が長く続いて心肥大がひどくなると、肥大して適応していた心臓がさらなる負担に適応しきれなくなり、ついには心不全に陥ります。高血圧により心肥大をきたした状態を高血圧性心疾患といい、心不全や不整脈の原因となります。
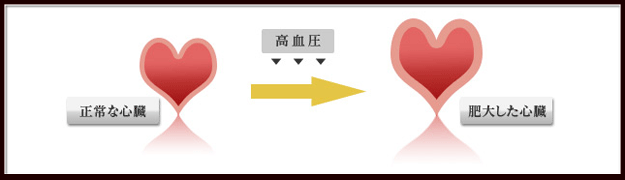
心臓は小さくてコンパクトなのが理想です。一度肥大した心臓でも、適切な高血圧治療により、心肥大の進行を止め、さらに元のスマートな心臓にすることも可能です。
★糖尿病★
糖類など炭水化物は、最少単位であるブドウ糖に分解して小腸から血液中に吸収されます。血液中に含まれるブドウ糖が血糖です。血液中のブドウ糖を細胞内に取り込み、血糖を下げる働きをするのがインスリンです。体の中で唯一、血糖を下げるホルモンです。
インスリンは、膵臓にあるランゲルハンス島のβ(ベータ)細胞から分泌されるホルモンで、血糖を細胞の中に取り込み、エネルギーに変える働きをします。インスリンの分泌が低下したり、インスリンの細胞への働きが低下して、血糖の上がる状態が糖尿病なのです。
◆糖尿病にはどんな種類があるの?
糖尿病には、子供の頃に発症して、インスリンの分泌が絶対的に不足するⅠ型糖尿病と、成人になってから発症して、インスリンの相対的不足とインスリンに対する抵抗性が増加するⅡ型糖尿病があります。また、ほかの病気や薬により起こる糖尿病を二次性糖尿病といいます。生活習慣病としての糖尿 病はⅡ型糖尿病で、日本人の糖尿病の約95%を占めています。
◆Ⅱ型糖尿病はどうして起こるの?
Ⅱ型糖尿病(以下糖尿病といえばこれを指します)になる人は、両親、兄弟が既にⅡ型糖尿病を罹っている場合が多く、その発症には遺伝的因子が大きな位置を占めていると考えられます。
糖尿病になりやすい遺伝的因子を持った人に、環境因子としての肥満・過食・運動不足・ストレスなどが加わると、インスリンの分泌が低下したり、インスリンに対する抵抗性が増大して、糖尿病が発症します。
★脂質異常症★
血液中には、コレステロールと中性脂肪の2種類の脂肪があります。いずれも”油”であるため、そのままでは”水”である血液には溶けません。そこで、”水”に溶けやすいタンパク質と粒子を作り、血液中を流れていきます。そのタンパク質をアポタンパクといい、脂肪と様々な割合で粒子を作っています。この粒子をリポタンパクと呼んでいます。
動脈硬化に関係が深いリポタンパクとして、低比重リポタンパク(LDL)と高比重リポタンパク(HDL)があります。
◆悪玉コレステロールと善玉コレステロール
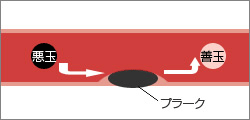 低比重リポタンパク質(LDL)に含まれるコレステロールを悪玉コレステロールと呼んでいます。この低比重リポ タンパク(LDL)は、酸化されて酸化LDLになり、血管の壁に取り込まれます。血管の壁に取り込まれた酸化LDLは、マクロファージという細胞に食べられ、蓄積していきます。この蓄積したものがプラークという血管の壁の”こぶ”になります。
低比重リポタンパク質(LDL)に含まれるコレステロールを悪玉コレステロールと呼んでいます。この低比重リポ タンパク(LDL)は、酸化されて酸化LDLになり、血管の壁に取り込まれます。血管の壁に取り込まれた酸化LDLは、マクロファージという細胞に食べられ、蓄積していきます。この蓄積したものがプラークという血管の壁の”こぶ”になります。このように、動脈硬化を進展させるため、悪玉コレステロールと呼ばれています。一方、高比重リポタンパク(HDL)に含まれるコレステロールを善玉コレステロールと呼んでいます。高比重リポタンパク(HDL)は、血管の壁に蓄積したコレステロールを血液中に引き戻し、肝臓で処理します。動脈硬化の進展を防ぐため、善玉コレステロールと呼んでいます。
★肥満と肥満症★
「肥満」とは、身長に比べ体重の割合が異常に大きいことをいいます。
高血圧や糖尿病、脂質異常症など他の病気を合併している場合、肥満の治療が必要となり、医学的に「肥満症」という病気として扱われます。但し、ただ単に太っているだけの「肥満」も、生活習慣病の中では、れっきとした病気と考えた方がいいでしょう。
◆なぜ、肥満はおこるの?
糖分は分解されてブドウ糖に変わります。ブドウ糖は脳や筋肉の働きに欠かすことのできないエネルギー源です。血液中のブドウ糖を体の組織に取り入れるために必要になるのが、膵臓から分泌されるインスリンというホルモンです。ブドウ糖はこのインスリンの働きで代謝され、最終的には水と二酸化 炭素になります。代謝されなかったブドウ糖は、グリコーゲンや中性脂肪となって、体内に貯蔵されます。
原始時代には人類は常に飢餓にさらされていました。食物から得たエネルギー源を無駄にせず蓄積し、わずかずつ効率よく利用することが、飢餓を切り抜ける上で必須であったのです。このような体質は「倹約遺伝子」として、遺伝的に引き継がれています。
しかし、このような体質を持つ現代人が栄養過多、運動不足の状況におかれると、蓄積したエネルギー源を使うことはほとんどなく、消費されない中性脂肪が貯まる一方になるわけです。
◆肥満症の診断基準は?
肥満症の診断には、まず最初に肥満かどうかの判定を行います。
その際、使われる指標が「BMI(Body Mass Index)」と言われるものです。これは国際的にも広く通用する体格指数なのです。

◆内臓脂肪の蓄積する方が危険! ~肥満症の診断~
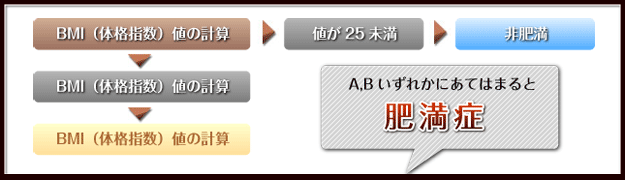
A)肥満による健康障害(高血圧、糖尿病、脂質異常症の合併)
B)内臓脂肪を測定する
1. 簡易検査:ウエスト周囲径を測定し、男性で85cm以上、女性で90cm以上
2. 腹部CTスキャン:臍(ヘソ)の部分でCTの断面像を撮影し、内臓脂肪の面積が100cm以上あれば、⇒「内臓脂肪型肥満症」